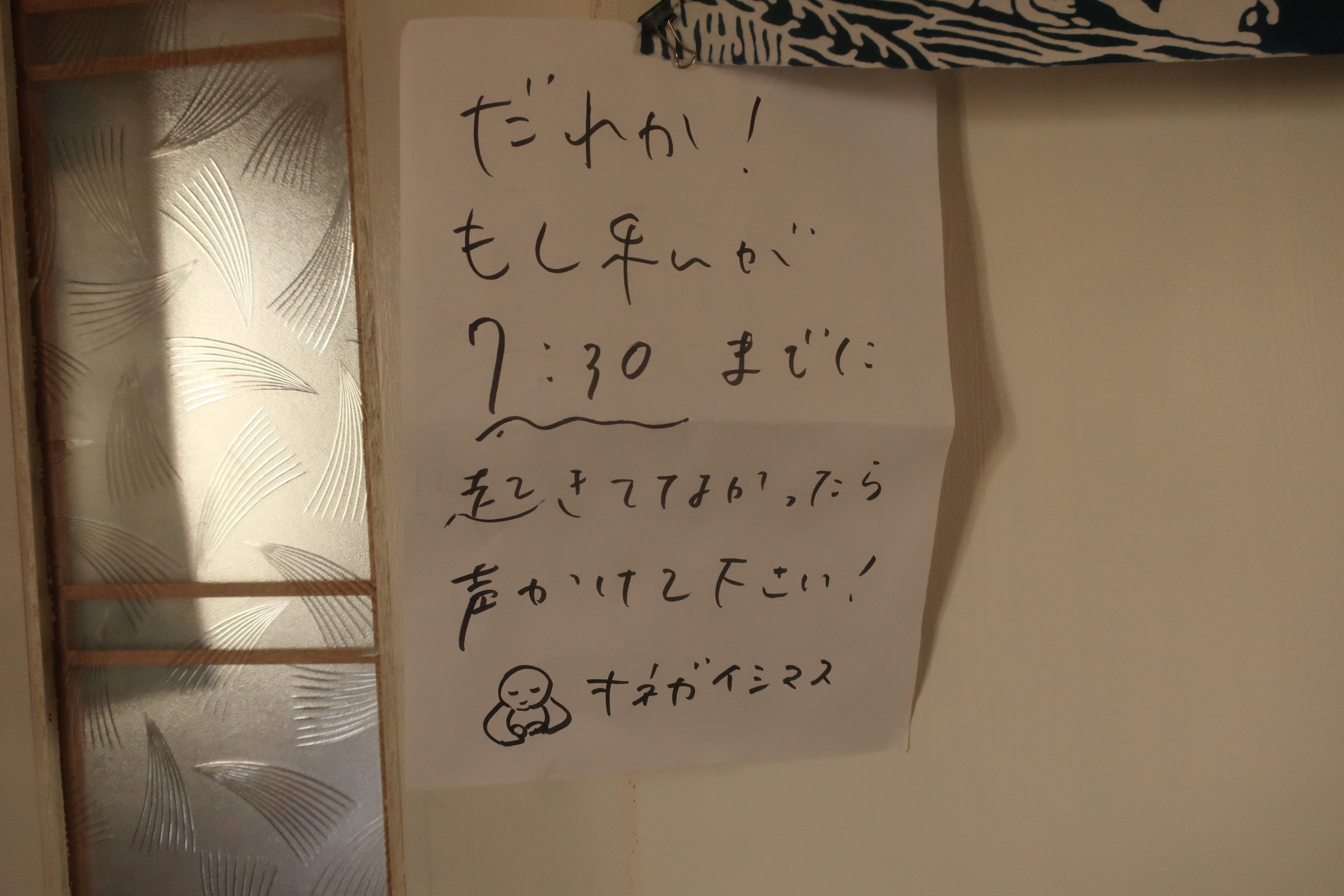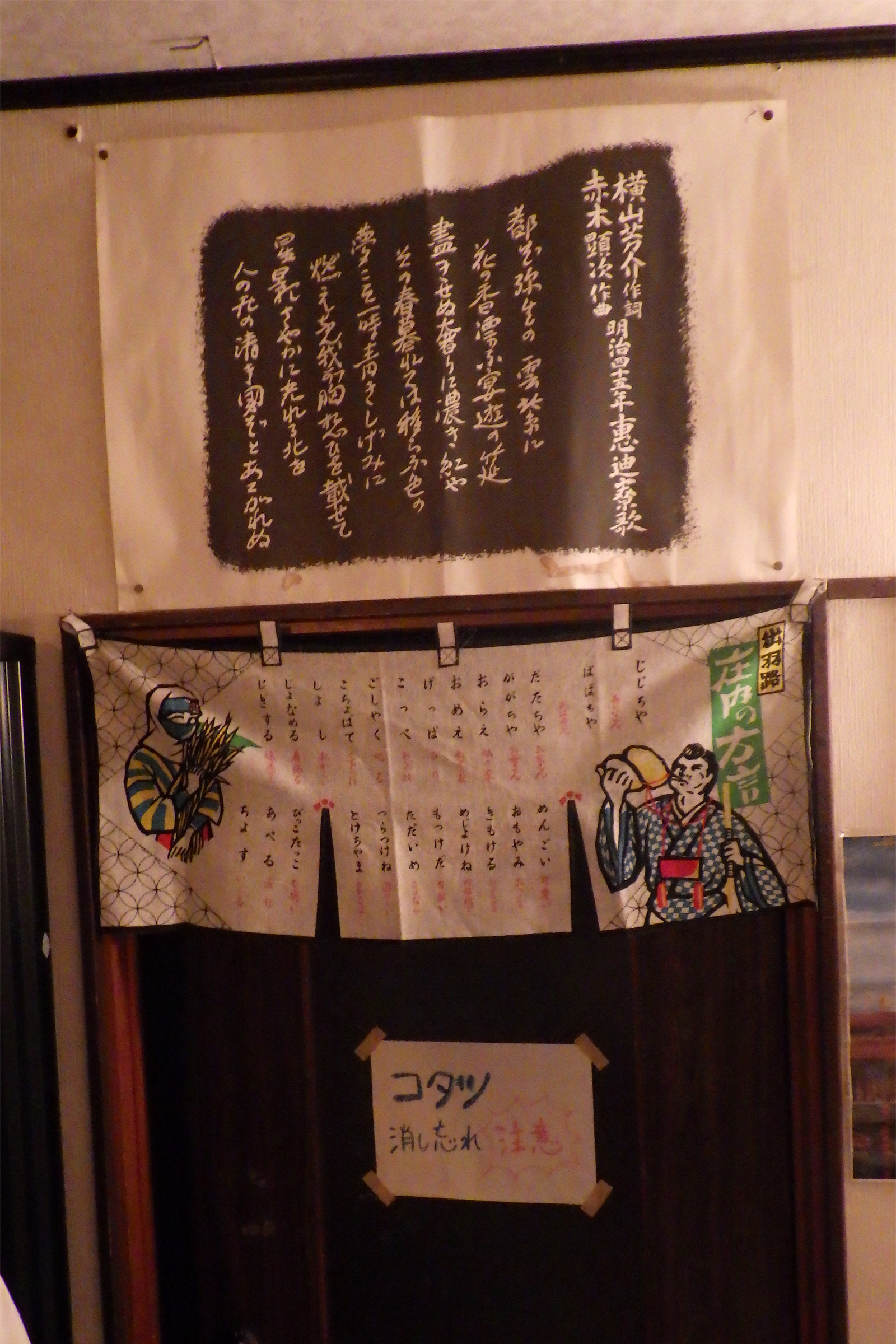ちえんそうにかえろ
五十嵐 宥樹
「デモクラシーとユキムシ」
今シーズン初の煙突掃除をした。シーズン、というのは薪ストーブを使う期間のことで、だいたい毎年10月くらいから春の間まで。春がいつまでも寒い年はゴールデンウイークくらいまで断続的に火を焚いていたりもする。
先月は煙突掃除をしないまま、火を焚いていた。今春の汚れそのままに。これは非常に居心地の悪いことで、火にあたりながらもなんとなく落ち着かない日々を過ごしていた。もちろん、煙突のつまりのために火が勢いよく燃えないとか、煙道火災の恐れがあるとか、煙突の状態を確認していないまま薪をくべている気持ち悪さもあるのだが、それだけではない。この家には、冬が来る前に「ヒノカミに挨拶」をするのが慣わしになっている。だのに、それをしないまま火を使いはじめていたこと、つまりある種のタブーを侵していたことへの背徳感のようなものがあったためと思う。
「ヒノカミ」というのは、いつぞや或る住人が他の家の慣わしを伝え聞いてきて、この家に持ち込んだ起源の明らかな慣習である。起源も出自も明らかなのに、数年で住人を気味悪がらせる効能(チカラというべき?)があるのだから、カミなるものはやはりおそろしい。
ヒトは、ストーブを使い始めるまえに、煙突の煤をブラシで掻きだし、ストーブ台やその周辺を掃除することで、ヒノカミにこの冬の火の元安全を祈願する。あれ、たしか元の家では「常に火の元、周辺を清潔にして、ヒノカミに失礼がないように」するとか日常の心掛けだったような気もするが、怠慢が前提のこの家では、あっという間に年中行事に変質してしまっている。もちろん、毎月の煙突掃除の折には、ストーブやその周囲も掃除してはいるのだが。兎にも角にも、火の周りを綺麗にとの心掛けは大切にしたい。
先月は煙突掃除をしないまま、火を焚いていた。今春の汚れそのままに。これは非常に居心地の悪いことで、火にあたりながらもなんとなく落ち着かない日々を過ごしていた。もちろん、煙突のつまりのために火が勢いよく燃えないとか、煙道火災の恐れがあるとか、煙突の状態を確認していないまま薪をくべている気持ち悪さもあるのだが、それだけではない。この家には、冬が来る前に「ヒノカミに挨拶」をするのが慣わしになっている。だのに、それをしないまま火を使いはじめていたこと、つまりある種のタブーを侵していたことへの背徳感のようなものがあったためと思う。
「ヒノカミ」というのは、いつぞや或る住人が他の家の慣わしを伝え聞いてきて、この家に持ち込んだ起源の明らかな慣習である。起源も出自も明らかなのに、数年で住人を気味悪がらせる効能(チカラというべき?)があるのだから、カミなるものはやはりおそろしい。
ヒトは、ストーブを使い始めるまえに、煙突の煤をブラシで掻きだし、ストーブ台やその周辺を掃除することで、ヒノカミにこの冬の火の元安全を祈願する。あれ、たしか元の家では「常に火の元、周辺を清潔にして、ヒノカミに失礼がないように」するとか日常の心掛けだったような気もするが、怠慢が前提のこの家では、あっという間に年中行事に変質してしまっている。もちろん、毎月の煙突掃除の折には、ストーブやその周囲も掃除してはいるのだが。兎にも角にも、火の周りを綺麗にとの心掛けは大切にしたい。
今朝の煙突掃除は1時間程度。まだ根雪になっていないので、苦でもなかった。これが極寒の1月、2月ともなると、気合の要る仕事になる。思うだけでも手がかじかむ。が、煙突の煤やタールをこそぎきり、勢いよく煙が排出される煙突で焚き始めるストーブの快音を想えば、これもまた冬の風物詩といえよう。
煤などの阻害物が一切ない煙突を搭載したストーブは、焚き口から「ぼっぼっぼ」っと機関車のような音を出して薪を勢いよく燃やしてくれる。ストーブが薪をむしゃむしゃと美味しそうに食べているようにも見えるから愛くるしい。
ティファールよりもすぐに湧く湯で飲む茶は格別だ。冷えた体をたちどころに芯から温めてくれる。寒いのは嫌いだが、この瞬間だけは待ち遠しく感じている自分がいる。薪を焚くようになってから、冬への苦手意識が半減した。嘘でない。
雪虫が飛べば、自分の気分も低調で冬仕様だ。これからまた長い冬がはじまる。まずは第一関門の冬至を越すまでどれだけ前向きでいられるか。そこから春を待たずに、「もう春か」といった具合が望ましい。
冬が本番の造材シーズンもすぐそこまで来ている。ひいこら、言っている間に春が来そうな気もしている。冬が忙しいというのも悪くないのかもしれない。
今年もあと2か月。さようなら2025年。元日の書初め、今年の一字は「御す」だった。残りの日々をうまく御せるかな。
煤などの阻害物が一切ない煙突を搭載したストーブは、焚き口から「ぼっぼっぼ」っと機関車のような音を出して薪を勢いよく燃やしてくれる。ストーブが薪をむしゃむしゃと美味しそうに食べているようにも見えるから愛くるしい。
ティファールよりもすぐに湧く湯で飲む茶は格別だ。冷えた体をたちどころに芯から温めてくれる。寒いのは嫌いだが、この瞬間だけは待ち遠しく感じている自分がいる。薪を焚くようになってから、冬への苦手意識が半減した。嘘でない。
雪虫が飛べば、自分の気分も低調で冬仕様だ。これからまた長い冬がはじまる。まずは第一関門の冬至を越すまでどれだけ前向きでいられるか。そこから春を待たずに、「もう春か」といった具合が望ましい。
冬が本番の造材シーズンもすぐそこまで来ている。ひいこら、言っている間に春が来そうな気もしている。冬が忙しいというのも悪くないのかもしれない。
今年もあと2か月。さようなら2025年。元日の書初め、今年の一字は「御す」だった。残りの日々をうまく御せるかな。
「7月10日の薪仕事」
現実逃避で薪を割る。塀の内側に放置していた、どんころ(丸太)をようやく片づけた。朝の涼しい時間だけ、と思って割り始めてみると、手のかかる節榑(ふしくれ)ばかりで、結局一日仕事になってしまった。
今朝は4時に起きて、5時に日課のラジオ体操第一。晴れやかな気分で斧を手にとる。日の出が少し、遅くなっているのを感じる。今年の夏至は6月21日だったそうだ。
日々、暇を見つけてちょぼちょぼと薪割りをしていると、無意識のうちに大物や節の多い玉を避けているようで、今日はくせ者ばかりを相手する羽目になった。薪割りクサビを叩き込んで割っていかないとならないようなものばかりで、いちいち苦労する。カコーンという音と同時に、割った薪が吹っ飛んでいく、あの、爽快感とは無縁の、シブい薪割りである。今日のお相手はカラマツ、アカエゾマツ、ミズナラと少しの白樺。
玄関フードに積み上げた薪の前で耳を澄ますと、コリコリっと音を立てて乾いていく薪が割れる音が聞こえる。何とも気分が良いものだが、今日はそんな音に耳を貸す余裕もなく、黙々とヒネた丸太に斧を叩きこんでいく。節でごつごつのナラに斧を振り下ろすと、こちらの節々が軋むような衝撃が跳ね返ってくる。原稿を書いている今、背骨と右肩あたりにじんわりと今日の疲労が滲んでいる。
今朝は4時に起きて、5時に日課のラジオ体操第一。晴れやかな気分で斧を手にとる。日の出が少し、遅くなっているのを感じる。今年の夏至は6月21日だったそうだ。
日々、暇を見つけてちょぼちょぼと薪割りをしていると、無意識のうちに大物や節の多い玉を避けているようで、今日はくせ者ばかりを相手する羽目になった。薪割りクサビを叩き込んで割っていかないとならないようなものばかりで、いちいち苦労する。カコーンという音と同時に、割った薪が吹っ飛んでいく、あの、爽快感とは無縁の、シブい薪割りである。今日のお相手はカラマツ、アカエゾマツ、ミズナラと少しの白樺。
玄関フードに積み上げた薪の前で耳を澄ますと、コリコリっと音を立てて乾いていく薪が割れる音が聞こえる。何とも気分が良いものだが、今日はそんな音に耳を貸す余裕もなく、黙々とヒネた丸太に斧を叩きこんでいく。節でごつごつのナラに斧を振り下ろすと、こちらの節々が軋むような衝撃が跳ね返ってくる。原稿を書いている今、背骨と右肩あたりにじんわりと今日の疲労が滲んでいる。
これまでに割った分につぎ足すように、薪を積み重ねてゆく。結局、塀の外側と、家の周囲に積み上げた分で合計14立米の薪になった。1m×1m×1mで1立米。積み上げた薪の縦横の積と、薪の長さ約0.4mをさらにかけて、一つの薪山の量を把握する。1年で7立米くらいの薪を焚くので、これで2冬は越せることになる。安心、安心。
普段から、薪不足を恐れて、ついついもらえる木があると貯め込んでしまう。近いうちに拠点の移動を考えているので、この薪の量は嬉しい悲鳴。しばらくはあくせく丸太を探して歩かなくてよいのが、ありがたいといえばありがたい。
現実逃避しないとできない仕事、というのはある気がする。今週は、そればっかりだった。
普段から、薪不足を恐れて、ついついもらえる木があると貯め込んでしまう。近いうちに拠点の移動を考えているので、この薪の量は嬉しい悲鳴。しばらくはあくせく丸太を探して歩かなくてよいのが、ありがたいといえばありがたい。
現実逃避しないとできない仕事、というのはある気がする。今週は、そればっかりだった。
「6月最後のたきのぼり」
6月最後の日、後輩のピンピンと沢登りへ。学生時代に一度登った30mほどの滝を登る。
ピンピンにロープを伸ばしてもらい、自分があとを追う。大きな滝を登るのは今日が初めてというピンピン。途中で岩の割れ目にハーケンを打ち込み、危なげなく支点をとっていく。
彼と結ばれたロープを手繰ったり伸ばしたりして、飛沫を浴びながら空を見上げる。雨の中の滝登り。
ピンピンが3つ目の支点を打ち込み始めたころ、雨具のフードを叩く飛沫の音が強くなる。私が登り始めるころには、白かった滝が茶色くなり始めていたところだった。
ロープがいっぱいに手繰られたのを確認して、ピンピンが待つ場所めがけて岩を攀じりはじめる。
水に磨かれて丸くなった岩肌に手足を乗せて、少しずつ高度を上げる。滝の落ち口まであと3メートル。流水の中の手がかりを掴んだところで足がとまる。とめどなく流れる滝に頭を押さえつけられて、水の中の手を次の手がかりへ伸ばすことを躊躇ってしまう。
次の足も水の中に置こうとすると、流水で足払いをくらいそうになる。
あれ・・・・? こわい。
もう何年も前の話だが、水流に剝がされて滝から落ちた友人の姿が頭の中で再生される。あの時も確か雨が降っていて、同じように彼が滝を抜ける直前の一手で体を引き上げようとした瞬間だった。滝から落ちた人を見たのはそれっきりだが、あの「ぽろっ」という音がしそうな光景を思い出して気味が悪くなる。
学生時代に来た時は、恐怖感なんかなくて、些かのスリルをただ楽しんでいたというのに、正直全然楽しくない。滝登りをせずに帰ろうとするピンピンを煽っていた、ついさっきの自分を呪う。
バララっと水が肩を叩く音で現実に引き戻される。岩に張り付く時間が長いほど、追い込まれることくらいは知っている。結局、意を決して直上を果たす。どっ、と徒労のため息が漏れた。
学生時代は楽しくて仕方なかったこういう沢登りが、なぜ楽しめなくなったのだろう。あの頃は、沢登りに熱中していて、沢に行って帰っては、次はどこへ行こうかと、記録を漁っていた。別段強くは無かったが、とにかく沢のことを考えていたし、沢に行きたくて仕方なかった。
ピンピンにロープを伸ばしてもらい、自分があとを追う。大きな滝を登るのは今日が初めてというピンピン。途中で岩の割れ目にハーケンを打ち込み、危なげなく支点をとっていく。
彼と結ばれたロープを手繰ったり伸ばしたりして、飛沫を浴びながら空を見上げる。雨の中の滝登り。
ピンピンが3つ目の支点を打ち込み始めたころ、雨具のフードを叩く飛沫の音が強くなる。私が登り始めるころには、白かった滝が茶色くなり始めていたところだった。
ロープがいっぱいに手繰られたのを確認して、ピンピンが待つ場所めがけて岩を攀じりはじめる。
水に磨かれて丸くなった岩肌に手足を乗せて、少しずつ高度を上げる。滝の落ち口まであと3メートル。流水の中の手がかりを掴んだところで足がとまる。とめどなく流れる滝に頭を押さえつけられて、水の中の手を次の手がかりへ伸ばすことを躊躇ってしまう。
次の足も水の中に置こうとすると、流水で足払いをくらいそうになる。
あれ・・・・? こわい。
もう何年も前の話だが、水流に剝がされて滝から落ちた友人の姿が頭の中で再生される。あの時も確か雨が降っていて、同じように彼が滝を抜ける直前の一手で体を引き上げようとした瞬間だった。滝から落ちた人を見たのはそれっきりだが、あの「ぽろっ」という音がしそうな光景を思い出して気味が悪くなる。
学生時代に来た時は、恐怖感なんかなくて、些かのスリルをただ楽しんでいたというのに、正直全然楽しくない。滝登りをせずに帰ろうとするピンピンを煽っていた、ついさっきの自分を呪う。
バララっと水が肩を叩く音で現実に引き戻される。岩に張り付く時間が長いほど、追い込まれることくらいは知っている。結局、意を決して直上を果たす。どっ、と徒労のため息が漏れた。
学生時代は楽しくて仕方なかったこういう沢登りが、なぜ楽しめなくなったのだろう。あの頃は、沢登りに熱中していて、沢に行って帰っては、次はどこへ行こうかと、記録を漁っていた。別段強くは無かったが、とにかく沢のことを考えていたし、沢に行きたくて仕方なかった。
最近は、山仕事に熱中している。森に行って帰っては、明日はどの木を伐ろうか、なんて考えながらチェンソーの手入れをしたりしている。ここ最近は、今の現場、先々の現場について考えてばかりいる。正直、今回沢を歩いているときも「山仕事で使う自分の身体を消耗したくないし、どこも欠損させたくない」という頭でいっぱいだった。
山仕事は危険である。52/1000という労災の保険料の高さがそれを表している。昨年末から春までの造材期間中、毎月一人以上の死亡災害が、道内ではあった。
日々の仕事では、危険が近くに潜んでいないか目を配り、極力排除しようとすることに神経をすり減らしている。伐採作業や運び出しの仕事などはとくにそうだ。それでもヒヤリハットがあった日は、しばらく自責の念とともに薄気味悪さを引きずることになる。帰りの車に乗ったらぐったりする日もある。
そんな生活を送っている余暇の日に、こんな危ないことをして楽しめないのは当然で、「俺なにやってんだろう」的な自分に遭遇することになってしまったのである。山仕事が文字通り命懸けなのに、レジャーの沢で冒険してられるか、というわけだ。ピンピンが沢に命を懸けるくらい熱中しているとすれば、沢=活動 に対する価値観のズレから、「ザイルパートナー(こんな格好いい言葉、げんじつに使ったことない)解消」待ったなし、となるのであろう。
思えば、学生時代は大学構内に楽しいことなどなく、野外に自分の生きる場所を探してほっつき歩いていた。山や川に行くために札幌で日々を過ごし、そこにいる間だけ、本当の充足感のようなものを得ていた気がする。町で得られないそれを酒でごまかした。
思えば、学生時代は大学構内に楽しいことなどなく、野外に自分の生きる場所を探してほっつき歩いていた。山や川に行くために札幌で日々を過ごし、そこにいる間だけ、本当の充足感のようなものを得ていた気がする。町で得られないそれを酒でごまかした。
今は、山仕事が楽しくて、森で働く日々に満足している。へとへとになるまで山で動くのが気持ちいいので、自然と夜更かしや酒をやらなくなっている。
まだ町が目覚めていない夜明けの朝日を、独り占めできる爽快感。
からだの中から ぐんぐん と音がする。こうなりゃ遅くまで酒なんかのんでいられない。朝5時に自主的にする「ラジオ体操第一」は、労働後のビール一気飲みくらい気持ちがいい。
かつて山に逃げていた自分は、近ごろヤマで生きている。大滝に打たれて自分の影をみた。ピンピンありがとう。
山仕事は危険である。52/1000という労災の保険料の高さがそれを表している。昨年末から春までの造材期間中、毎月一人以上の死亡災害が、道内ではあった。
日々の仕事では、危険が近くに潜んでいないか目を配り、極力排除しようとすることに神経をすり減らしている。伐採作業や運び出しの仕事などはとくにそうだ。それでもヒヤリハットがあった日は、しばらく自責の念とともに薄気味悪さを引きずることになる。帰りの車に乗ったらぐったりする日もある。
そんな生活を送っている余暇の日に、こんな危ないことをして楽しめないのは当然で、「俺なにやってんだろう」的な自分に遭遇することになってしまったのである。山仕事が文字通り命懸けなのに、レジャーの沢で冒険してられるか、というわけだ。ピンピンが沢に命を懸けるくらい熱中しているとすれば、沢=活動 に対する価値観のズレから、「ザイルパートナー(こんな格好いい言葉、げんじつに使ったことない)解消」待ったなし、となるのであろう。
思えば、学生時代は大学構内に楽しいことなどなく、野外に自分の生きる場所を探してほっつき歩いていた。山や川に行くために札幌で日々を過ごし、そこにいる間だけ、本当の充足感のようなものを得ていた気がする。町で得られないそれを酒でごまかした。
思えば、学生時代は大学構内に楽しいことなどなく、野外に自分の生きる場所を探してほっつき歩いていた。山や川に行くために札幌で日々を過ごし、そこにいる間だけ、本当の充足感のようなものを得ていた気がする。町で得られないそれを酒でごまかした。
今は、山仕事が楽しくて、森で働く日々に満足している。へとへとになるまで山で動くのが気持ちいいので、自然と夜更かしや酒をやらなくなっている。
まだ町が目覚めていない夜明けの朝日を、独り占めできる爽快感。
からだの中から ぐんぐん と音がする。こうなりゃ遅くまで酒なんかのんでいられない。朝5時に自主的にする「ラジオ体操第一」は、労働後のビール一気飲みくらい気持ちがいい。
かつて山に逃げていた自分は、近ごろヤマで生きている。大滝に打たれて自分の影をみた。ピンピンありがとう。
「6月16日の畦道」
今日は田んぼの畔の草刈り。ここ数年、ご近所のお米農家さんのところで種落としや田植えの手伝いをさせてもらっている。その延長で、今日は畔の草刈りを任せてもらう。
田植え直後の稲はまだ小さいので、田んぼに張られた水が鏡のように空を映し出す。北海道のウユニ湖がそこらじゅうに。
生まれ育った郡山も盆地で、周りは田んぼが多かったので、初夏の稲の匂いを嗅ぐと気分が落ち着く。この先森の中に引っ越すことを決めているが、この匂いを嗅ぐためだけに、田園地帯でも定期的に仕事を続けるのもよいな、と思っている。
小学校の通学路、家から学校までの間には小さな田んぼが何枚もあった。畦道を通ると、道路を歩くよりもショートカットすることができたし、狭く盛り上がった土の道は一本橋のようで面白く、ランドセルを背負ったままよく歩いた。子供ながらに人の土地に侵入している背徳感のようなものを感じて、「いいのかなあ~」なんて思いながら歩くのも愉快だった。今では通学路の田んぼの多くが分譲住宅に変わっている。
朝いちばん、持参したUハンドルの刈り払い機で畔を刈り始めるも、なんともうまくいかない。畔の法面と水面の境界あたりの、切り立った畔壁に生える草を刈るのに、無理な体制をしないと刃が草に届かないのだ。
結局、見かねた地主さんが一本竿式の刈り払い機を貸してくれる。エンジンは背中に背負えるタイプで、米農家さんが使っているのをよく見るやつだ。思ったよりも背中のエンジンは重くなく、排熱も気にならない。今までの仕事はなんだったんだというくらい捗る。
Uハンドルは山林の草刈り向きで、広い面積を大振りで刈り進んでいくのに向いている。一方、一本竿式の刈り払い機は畦道のような狭い場所で、小回りを利かせて草を刈っていくのに向いている、、、というのがよくわかった。掃除機をかけるような感覚で、田んぼの周囲の草をバタバタと倒していく。草むらからカエルが田んぼに避難していくたび、ほんの少し申し訳ない気持ちになる。一匹のカエルの右腕を切ってしまった。かたわになっても平泳ぎで、田んぼ沖を目指して泳いでいった。
生まれ育った郡山も盆地で、周りは田んぼが多かったので、初夏の稲の匂いを嗅ぐと気分が落ち着く。この先森の中に引っ越すことを決めているが、この匂いを嗅ぐためだけに、田園地帯でも定期的に仕事を続けるのもよいな、と思っている。
小学校の通学路、家から学校までの間には小さな田んぼが何枚もあった。畦道を通ると、道路を歩くよりもショートカットすることができたし、狭く盛り上がった土の道は一本橋のようで面白く、ランドセルを背負ったままよく歩いた。子供ながらに人の土地に侵入している背徳感のようなものを感じて、「いいのかなあ~」なんて思いながら歩くのも愉快だった。今では通学路の田んぼの多くが分譲住宅に変わっている。
朝いちばん、持参したUハンドルの刈り払い機で畔を刈り始めるも、なんともうまくいかない。畔の法面と水面の境界あたりの、切り立った畔壁に生える草を刈るのに、無理な体制をしないと刃が草に届かないのだ。
結局、見かねた地主さんが一本竿式の刈り払い機を貸してくれる。エンジンは背中に背負えるタイプで、米農家さんが使っているのをよく見るやつだ。思ったよりも背中のエンジンは重くなく、排熱も気にならない。今までの仕事はなんだったんだというくらい捗る。
Uハンドルは山林の草刈り向きで、広い面積を大振りで刈り進んでいくのに向いている。一方、一本竿式の刈り払い機は畦道のような狭い場所で、小回りを利かせて草を刈っていくのに向いている、、、というのがよくわかった。掃除機をかけるような感覚で、田んぼの周囲の草をバタバタと倒していく。草むらからカエルが田んぼに避難していくたび、ほんの少し申し訳ない気持ちになる。一匹のカエルの右腕を切ってしまった。かたわになっても平泳ぎで、田んぼ沖を目指して泳いでいった。
一人(とりわけ孤食)は苦手だけど、一人作業は結構好きだ。草刈りとか、伐木とか、一人で黙々とできる肉体労働は苦にならない。無念無想、という感じでもなくて、頭は意外と賑やかしい。単純肉体作業のときはむしろ、よしなしごとを考えるともなく考えて、浮かんでは消えて、「なにかがわかる」という感じもたびたびあって、あっという間に時間が過ぎていく。山登りとか、川下りとか、焚火とかも、結局はそうなのかもしれない。文章を書きたいと思っているときは何も思い浮かばなくて、日々肉体労働をしているほうが何かと書き出したいことが出てきたりする。
頭上で本日何機目かのジェット機がすぐそばの空港へ降下していく。石でも投げたら当たりそうな距離に見えるほど頭上にクッキリと大きい。思い立ったら、ここから東京でも、ミャンマーでも、行けてしまうのだ。本当は。たまたま来週いっぱい、人に手伝ってもらう仕事があるから、できないだけで、衝動が高まったりしたら、突然ロシアに行ってしまったり、することもあるのだろうか。なんで、自分は草刈り機を放り投げて、飛行機に飛び乗ってしまわないのだろうか。たまにはいっそ、そういうことがあってもいいんじゃないかと思う。それをやってみたいと思うことと、そんなことは空想でしかないと、自分を狭く納めていること、その両方に、空恐ろしくなる。
夕方、日が傾き始めたので、1つの畔を仕上げて仕舞いにする。定時だから、ではなく、暗くなってきた、と思ったからやめる。時刻は18時を過ぎていた。続きは明日。夕方2時間も刈れば、「山側の田んぼ」は終わるだろう。残りは「線路わきの田んぼ」のほう。
帰り道、何枚もの田んぼを車窓から眺めながら家路につく。瞬間瞬間で、あの畔は刈りにくそうだな、とか、あそこは草ボーボーだな、とか頭で思う。少し畦道刈りをしただけで、「畦道eye」になってる。覚えた山菜を山で発見して「あっ」と思うのに近い。
自分でビニールハウスを解体したり建てたりしたピオス君は「ハウスeye」を獲得している。椅子張りしてるパト氏は「座面eye」を獲得している。・・・・
工事看板を見ると字面よりも、支柱に使われている垂木に目が行く。
・・・いろんな目を獲得したいと思う。
頭上で本日何機目かのジェット機がすぐそばの空港へ降下していく。石でも投げたら当たりそうな距離に見えるほど頭上にクッキリと大きい。思い立ったら、ここから東京でも、ミャンマーでも、行けてしまうのだ。本当は。たまたま来週いっぱい、人に手伝ってもらう仕事があるから、できないだけで、衝動が高まったりしたら、突然ロシアに行ってしまったり、することもあるのだろうか。なんで、自分は草刈り機を放り投げて、飛行機に飛び乗ってしまわないのだろうか。たまにはいっそ、そういうことがあってもいいんじゃないかと思う。それをやってみたいと思うことと、そんなことは空想でしかないと、自分を狭く納めていること、その両方に、空恐ろしくなる。
夕方、日が傾き始めたので、1つの畔を仕上げて仕舞いにする。定時だから、ではなく、暗くなってきた、と思ったからやめる。時刻は18時を過ぎていた。続きは明日。夕方2時間も刈れば、「山側の田んぼ」は終わるだろう。残りは「線路わきの田んぼ」のほう。
帰り道、何枚もの田んぼを車窓から眺めながら家路につく。瞬間瞬間で、あの畔は刈りにくそうだな、とか、あそこは草ボーボーだな、とか頭で思う。少し畦道刈りをしただけで、「畦道eye」になってる。覚えた山菜を山で発見して「あっ」と思うのに近い。
自分でビニールハウスを解体したり建てたりしたピオス君は「ハウスeye」を獲得している。椅子張りしてるパト氏は「座面eye」を獲得している。・・・・
工事看板を見ると字面よりも、支柱に使われている垂木に目が行く。
・・・いろんな目を獲得したいと思う。
「馬糞とピオス」
土砂降り予報が的中し、ヤマの現場は昼で切り上げてピオスの畑へ向かう。ピオス君は最近、うんこ集めにハマっている。特に馬糞がいいらしい。知り合いの馬屋さんのところへ、堆肥用のうんこを集めに行くというので同行する。年季の入った軽トラックを飛ばして雨上がりの道を行く。土壌流亡が道路に幾筋もの砂絵を描いていた。
馬屋さんの馬房と放牧地には全部でばんばが11頭。数年前に初めたと聞いて耳を疑うほどの老舗具合。
かあさんと立ち話をしているうちに、テンガロンのトオサン帰宅。その世代の人、特有の静かな気迫を身にまとっている。現役で一次産業やってる70オーバーの男はみんな同じ目をしていて、一度目が合うと容易には離せない。澄んだ瞳に吸い込まれそうに、なんてたとえがロマンスにはあるけれど、自分はいつもこうした爺さんの厳しくて優しい目に吸い寄せられている。労働が磨いた瞳に釘付けになる。
ピオス君持参の特大フォークでうんこをさらって軽トラックに放り込む。ピオス君、いい匂いだあ、いい匂いだあ、と嬉しそう。
ひと段落したところで雨雲が大粒を降らす。珍しい大雨にトオサン、白髭を揺らして笑っている。ハイライトの煙が一緒にゆらゆら揺れて、空へ消えていく。選果場で雨宿りをしながら馬談義、畑談義。わずかな会話の中から、多くのヒントを掴み取るため耳を澄ます。土砂降りが全てを叩くせいでトオサンの声がなかなか聞こえない。多くを語る人ではないが、多くを感じえた。またお邪魔したいと、たしかに思う。
馬屋さんの馬房と放牧地には全部でばんばが11頭。数年前に初めたと聞いて耳を疑うほどの老舗具合。
かあさんと立ち話をしているうちに、テンガロンのトオサン帰宅。その世代の人、特有の静かな気迫を身にまとっている。現役で一次産業やってる70オーバーの男はみんな同じ目をしていて、一度目が合うと容易には離せない。澄んだ瞳に吸い込まれそうに、なんてたとえがロマンスにはあるけれど、自分はいつもこうした爺さんの厳しくて優しい目に吸い寄せられている。労働が磨いた瞳に釘付けになる。
ピオス君持参の特大フォークでうんこをさらって軽トラックに放り込む。ピオス君、いい匂いだあ、いい匂いだあ、と嬉しそう。
ひと段落したところで雨雲が大粒を降らす。珍しい大雨にトオサン、白髭を揺らして笑っている。ハイライトの煙が一緒にゆらゆら揺れて、空へ消えていく。選果場で雨宿りをしながら馬談義、畑談義。わずかな会話の中から、多くのヒントを掴み取るため耳を澄ます。土砂降りが全てを叩くせいでトオサンの声がなかなか聞こえない。多くを語る人ではないが、多くを感じえた。またお邪魔したいと、たしかに思う。
馬糞堆肥で育てたというアスパラをお土産にもたせてくれた。生でかじると果物のような甘さが口に広がる。百姓駆け出しのピオスくんに「生でかじったこの味を覚えておけ。それだけ」って電話が入っていた。
軽トラックから、うんこを下ろすためにトラクターを操るピオス。後方確認しながらハンドルをおおきく回す姿を見て、涙こそ出なかったが目頭が熱くなり、驚く。
2021年の新年。島の飯場で。臭くて旨い焼酎の瓶を毎晩空にしながら無邪気に語りあっていた、、、なんてふりかえるのも正直ダサいんだけど、俺は山仕事で、おまえは畑か。なんてことを毎晩、意志か覚悟みたいなものを確認するためなのか、やたらに杯を重ねた、無為な20代後半の一瞬。それから背負子ひとつで北海道に上陸したお前が、今や5反の耕地を前にトラクターを操っている。去年の秋には笹薮だった地面が今では黒々とした畑に変わり、新品のポールが刺さり、マルチが敷かれている。定植されたトマトの苗が、黒い地面からにょきにょきと顔を出している。雨上がりの白い青をバックに、赤いトラクターが妙に映えていたせいなのか、そんな記憶、同居をはじめて、家を出て「暖簾分け」してからの今までが一挙に押し寄せてきて、心が動いたのかもしれない。―ピオス君は農夫になりました。
軽トラックから、うんこを下ろすためにトラクターを操るピオス。後方確認しながらハンドルをおおきく回す姿を見て、涙こそ出なかったが目頭が熱くなり、驚く。
2021年の新年。島の飯場で。臭くて旨い焼酎の瓶を毎晩空にしながら無邪気に語りあっていた、、、なんてふりかえるのも正直ダサいんだけど、俺は山仕事で、おまえは畑か。なんてことを毎晩、意志か覚悟みたいなものを確認するためなのか、やたらに杯を重ねた、無為な20代後半の一瞬。それから背負子ひとつで北海道に上陸したお前が、今や5反の耕地を前にトラクターを操っている。去年の秋には笹薮だった地面が今では黒々とした畑に変わり、新品のポールが刺さり、マルチが敷かれている。定植されたトマトの苗が、黒い地面からにょきにょきと顔を出している。雨上がりの白い青をバックに、赤いトラクターが妙に映えていたせいなのか、そんな記憶、同居をはじめて、家を出て「暖簾分け」してからの今までが一挙に押し寄せてきて、心が動いたのかもしれない。―ピオス君は農夫になりました。
「紙か木か」
300年前に作られた椅子が、修理を待っているのに出くわした。東北のとある工房で。 これから、職人の手で座面が張り替えられ「現役」として復活し、人の手に渡ろうとしている。木部の樹種が、何であるかまではわからなかったが、この木の存在している時間のなんと永いことか。
ごく当たり前の話として、山に生える木は生きている。光合成をして呼吸をし、他の木と菌類を通じたやり取りをして、生命活動を営んでいる。
樵は、木を切り倒すのが仕事だから、木の命を絶つのが業と言い換えることもできる。初めて市場に出す木を切らせてもらった現場で、その重大さに戸惑ったことを思い出した。 先達の樵によって植えられ、自分よりも長く生きているトドマツを切り倒す。目の前に横たわった長く大きな木の枝を払う。太さ、曲がり、腐れに応じて、丸太に分ける長さを決めていく。
8尺に伐ればパルプ材、12尺に伐れば建材になった。健康で通直な幹であれば迷いが少ないが、幹曲がりや断面に腐れがあると、判断に迷い、建材になれたかもしれない立派なパルプ材をいくつも作ってしまった気がする。
倒した樹木の「第二の人生」を決めるのは他でもない自分だった。
極端な言い方をすれば、自分が殺めた命が、人が暮らす家になるのか、ケツを拭く紙になるのか、決める権限が、樵にはあるのだ。そのことに慄いた。この気持ちに誇張は一切ない。大袈裟と思う向きもあるかもしれないが、それくらい、材として切り倒す樹木は、存在として大きい。
ごく当たり前の話として、山に生える木は生きている。光合成をして呼吸をし、他の木と菌類を通じたやり取りをして、生命活動を営んでいる。
樵は、木を切り倒すのが仕事だから、木の命を絶つのが業と言い換えることもできる。初めて市場に出す木を切らせてもらった現場で、その重大さに戸惑ったことを思い出した。 先達の樵によって植えられ、自分よりも長く生きているトドマツを切り倒す。目の前に横たわった長く大きな木の枝を払う。太さ、曲がり、腐れに応じて、丸太に分ける長さを決めていく。
8尺に伐ればパルプ材、12尺に伐れば建材になった。健康で通直な幹であれば迷いが少ないが、幹曲がりや断面に腐れがあると、判断に迷い、建材になれたかもしれない立派なパルプ材をいくつも作ってしまった気がする。
倒した樹木の「第二の人生」を決めるのは他でもない自分だった。
極端な言い方をすれば、自分が殺めた命が、人が暮らす家になるのか、ケツを拭く紙になるのか、決める権限が、樵にはあるのだ。そのことに慄いた。この気持ちに誇張は一切ない。大袈裟と思う向きもあるかもしれないが、それくらい、材として切り倒す樹木は、存在として大きい。
北海道は、150年近くにわたる収奪林業の結果、大木と呼べる気が本当に少ない。家具材として利用されることの多い広葉樹も、事情は同じである。
で、あるならば。樵としては、丸太作りの過程においては正しい感覚と判断で、家具や建材になれる丸太を「ちゃんと」生産する、というのが当たり前のマナーである。樹木に対しても、山主に対しても。
便所紙として流された紙は、人間の糞と共に焼却されて、その灰はセメントの原料になるようだ。私が便所紙にした木は土へは還れない。次世代の樹木を肥やせない。
私はこれから何百、何千もの樹を伐るのだろうし、その行き先だって、単純ではない。実際には、1本の木から建材とパルプ材の両方が取れることのほうが多いし、払った枝や残された梢はその場で土に還ったり、バイオマス燃料として熱に変わったりすることもある。
けれど、300年遺され、生まれ変わって活躍せんとしている椅子の木部を前にしては、沈黙して、初めての現場を思い出し、考えざるを得なかったのだ。そのように在り続ける木があるということを、駆け出しの私は死ぬまで忘れてはいけないと思う。
で、あるならば。樵としては、丸太作りの過程においては正しい感覚と判断で、家具や建材になれる丸太を「ちゃんと」生産する、というのが当たり前のマナーである。樹木に対しても、山主に対しても。
便所紙として流された紙は、人間の糞と共に焼却されて、その灰はセメントの原料になるようだ。私が便所紙にした木は土へは還れない。次世代の樹木を肥やせない。
私はこれから何百、何千もの樹を伐るのだろうし、その行き先だって、単純ではない。実際には、1本の木から建材とパルプ材の両方が取れることのほうが多いし、払った枝や残された梢はその場で土に還ったり、バイオマス燃料として熱に変わったりすることもある。
けれど、300年遺され、生まれ変わって活躍せんとしている椅子の木部を前にしては、沈黙して、初めての現場を思い出し、考えざるを得なかったのだ。そのように在り続ける木があるということを、駆け出しの私は死ぬまで忘れてはいけないと思う。
「ちえんそうー宣言」
出遅れてもなお、先延ばし
土地とのつながりあるのやら
死ぬまで生き抜く知恵がほしい
グローバルサプライチェーンとは位相の違う、どローカルな供給網が出来たらいい。
捉えきれないほど大きくなった 世界的なモノの流通網。生産と消費の輪っかは地球を何周も取り囲むほど膨大で、グルグルと回り続けている。⻭を食いしばってそれを駆動しているのは、誰で、恩恵を受けているのは誰か。それは、自分が爺さんになっても変わらないのか。
トレーサビリティなどなくても、認証制度などなくても、わかる範囲で、あればいい。友人が育てた野菜を食べ、自分が伐り、割った薪で冬を越してもらえたら。生活必需品の一切を賄うことは不可能でも、生産と消費の輪っこを、手元、足元に手繰り寄せながら生きてみたい。自給自足や、コミューンとはすこし違う生き方を模索する。
自分は木を伐る。その木で椅子を作れるヤツがいて、それに相方が座面を張る。無農薬有機野菜をつくる人がいるかと思えば、牛屋さんも向こうで手を振っている。伝統工法が好きな大工がいて、味にうるさい鹿撃ちがいる。その殆どがみんな、その卵にすぎない、駆け出しや見習いの若造だけど、頼もしい仲間が少しずつ集まり、胎動している。あるいは、よちよちしたり、つかまり立ちをしたりしている。
土地とのつながりあるのやら
死ぬまで生き抜く知恵がほしい
グローバルサプライチェーンとは位相の違う、どローカルな供給網が出来たらいい。
捉えきれないほど大きくなった 世界的なモノの流通網。生産と消費の輪っかは地球を何周も取り囲むほど膨大で、グルグルと回り続けている。⻭を食いしばってそれを駆動しているのは、誰で、恩恵を受けているのは誰か。それは、自分が爺さんになっても変わらないのか。
トレーサビリティなどなくても、認証制度などなくても、わかる範囲で、あればいい。友人が育てた野菜を食べ、自分が伐り、割った薪で冬を越してもらえたら。生活必需品の一切を賄うことは不可能でも、生産と消費の輪っこを、手元、足元に手繰り寄せながら生きてみたい。自給自足や、コミューンとはすこし違う生き方を模索する。
自分は木を伐る。その木で椅子を作れるヤツがいて、それに相方が座面を張る。無農薬有機野菜をつくる人がいるかと思えば、牛屋さんも向こうで手を振っている。伝統工法が好きな大工がいて、味にうるさい鹿撃ちがいる。その殆どがみんな、その卵にすぎない、駆け出しや見習いの若造だけど、頼もしい仲間が少しずつ集まり、胎動している。あるいは、よちよちしたり、つかまり立ちをしたりしている。
それぞれの業をもちよれば、健康で、文化的な、最低限度の生活を営むことができそうだ。寒い北の大地でも、凍えず、くいっぱぐれることなく、年を重ねることができるかもしれない。主食の米や、パンだって食いたい。たまには蕎⻨も。まだまだ仲間がいてほしい。
スロー何某とか、丁寧な何某とか、ライフスタイルとか、よく知らない。アイツの大好物がビッグマックだったとしても、そんなことは彼氏の勝手だとか。時代の流れは早い。そしてどんどん加速する。こちらは遅延がベースなので、基本的に周回遅れ。時代遅れでかまわない。一周回って最先端。そんな、気持ちで靴を履く。今日も働いて、汗をかく。
⻄日が差して、片付けをして、カラスが鳴いたら、ちえんそうにかえろ。
スロー何某とか、丁寧な何某とか、ライフスタイルとか、よく知らない。アイツの大好物がビッグマックだったとしても、そんなことは彼氏の勝手だとか。時代の流れは早い。そしてどんどん加速する。こちらは遅延がベースなので、基本的に周回遅れ。時代遅れでかまわない。一周回って最先端。そんな、気持ちで靴を履く。今日も働いて、汗をかく。
⻄日が差して、片付けをして、カラスが鳴いたら、ちえんそうにかえろ。
プロフィール : 五十嵐 宥樹
94年、福島県生まれ。
北海道に来て探検部に7年在籍。
卒部後は山仕事に魅せられている。
94年、福島県生まれ。
北海道に来て探検部に7年在籍。
卒部後は山仕事に魅せられている。